令和5年度優秀教員表彰(ベストティーチャー賞)
概要
鳴門教育大学は10月2日、令和5年度の優秀教員として吉井健治教授、栗原慶教授、皆川直凡教授の3名を表彰した。
優秀教員表彰は、教育・学生生活支援、研究等において優秀な教員に対し毎年度実施している制度。
吉井教授は、心理臨床コース臨床心理学領域に所属し、大学院で臨床心理士及び公認心理師の養成、教育相談の実践的力量を有する現職教員の育成に尽力してきた。生徒指導支援センター所長またはスタッフとしては、附属学校スクールカウンセラーの運営・活動に多大な貢献を行い、附属学校の教育活動を支えてきた。地域貢献では、県内の様々な不登校児童生徒支援事業において中心的な役割を務めている。また、教員のメンタルヘルス問題やいじめ・不登校に関する保護者対応にも貢献している。
栗原教授は、美術科教育コースに所属し、旧修士課程及び教職大学院、学校教育学部において、工芸分野に関する教育と研究を行ってきた。特に近年は、日本伝統工芸展での継続した入選や伝統工芸四国展での受賞、公立美術館における企画個展の開催など、陶芸の実制作において顕著な業績をあげている。また、2022年度からは、教育実習総合支援センター教職大学院(教科・総合系)実習部門主任として、教職大学院での実習運営に貢献している。この他、四国国立5大学連携による連携教職課程設置準備WG(美術)委員等、大学運営においても尽力している。
皆川教授は、学習指導力・ICT教育実践力開発コースに所属し、教員志望の学生・院生、及び現職教員の院生への教育と研究指導に携わってきた。着任以来多数の学生・院生の研究指導を行っている。学部教育ではWG主査として「教育実践演習」の開設と実質化を取り組んだ。GPや大学院教育に係るタスクフォースの委員を歴任し、連合大学院では副研究科長を務めた。また、2022年度に開設された教職大学院遠隔教育プログラムについては、学習指導力・ICT教育実践力開発コースのコース長として遠隔教育プログラム院生の指導に先導的に取り組み、伴走型指導実践に貢献している。これらの実績がそれぞれ評価された。
表彰式では、受賞者から、これまでの謝辞や教育研究への思い、今後の抱負等が述べられた。
受賞者の業績や教育・研究手法は広く公開し、学内教員の資質向上に繋げていくこととしている。

(前列左から栗原教授、佐古学長、吉井教授、皆川教授
後列左から美馬理事、梅津理事、田中理事、高橋事務局長)
受賞者の紹介
優秀教員表彰(ベストティーチャー賞)
| 氏名 | 吉井 健治 教授 |
| 所属専攻 |
人間教育専攻 |
| 所属コース |
心理臨床コース(臨床心理学) |
| 写真 | 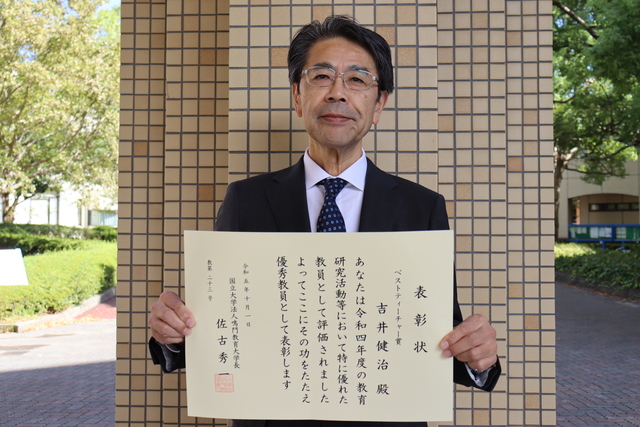 |
|
受賞理由 及び 優れた教育手法 |
吉井健治氏は、心理臨床コース臨床心理学領域に所属し、専門は臨床心理学である。 氏は、大学院で臨床心理士及び公認心理師の養成、教育相談の実践的力量を有する現職教員の育成に尽力してきた。学部授業では「教育相談論」を担当した。こうした学生の教育において、「不登校の子どもの心とつながるー支援者のための十二の技ー」(単著、金剛出版、2017年)をテキストとして活用し、不登校への理解と対応に努めてきた。 生徒指導支援センター所長またはスタッフとして、附属学校スクールカウンセラーの運営・活動に多大な貢献を行い、附属学校の教育活動を支えてきた。地域貢献では、県内の様々な不登校児童生徒支援事業において中心的な役割を務めている。また、教員のメンタルヘルス問題やいじめ・不登校に関する保護者対応にも貢献している。 以上のことから、吉井健治氏をベストティーチャーとして選定した。 |
| 受賞者のコメント |
このような賞をいただき、たいへん光栄に感じております。本学に2001年に着任し、いま23年目になります。私は、不登校やスクールカウンセリングなどを専門とし、何事にもベストを尽くしたいという気持ちで教育・研究・臨床に取り組んできました。この間、何とか無事に過ごすことができたのは、多くの皆様に支えられてきたからであり、心より感謝を申し上げます。 本学の心理臨床コース臨床心理学領域では、臨床心理士と公認心理師の両方の養成を行っています。2017年施行の公認心理師法によって国家資格の公認心理師が誕生しました。このような期待に応えるため、本学大学院でも新規の講義科目及び心理実習が増え、関係教職員の職務が大変充実してきているところです。 臨床心理学領域ではチーム学校の一員としてのスクールカウンセラーの養成も行っていますので、本学の教員養成をはじめ学校の教職員との連携協力において、今後も積極的に取り組んでいきたいと思います。この度の受賞を契機に、新たな気持ちで大学の発展や社会貢献に精一杯努めてまいります。 |
| 氏名 | 栗原 慶 教授 |
| 所属専攻 | 高度学校教育実践専攻 |
| 所属コース | 美術科教育コース |
| 写真 | 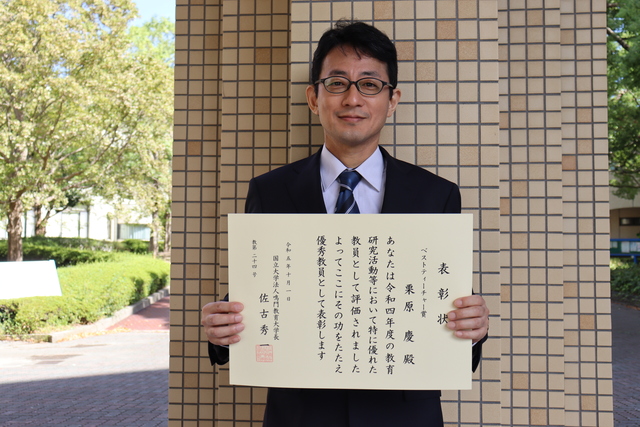 |
|
受賞理由 及び 優れた教育手法 |
栗原慶氏は美術科教育コースに所属し、専門分野は工芸(陶芸)である。 氏は、本学へ2012年4月に着任以来、旧修士課程及び教職大学院、学校教育学部において、工芸分野に関する教育と研究を行ってきた。特に近年は、日本伝統工芸展での継続した入選や伝統工芸四国展での受賞、公立美術館における企画個展の開催など、陶芸の実制作において顕著な業績をあげている。これらの制作発表時の解説や報道の機会を通して、工芸の社会的価値の認知に努めている。 また2022年度からは、教育実習総合支援センター教職大学院(教科・総合系)実習部門主任として、教職大学院での実習運営に貢献している。この他、四国国立5大学連携による連携教職課程設置準備WG(美術)委員や、教職大学院カリキュラム改編TFメンバーなど、大学運営においても尽力してきた。 以上のことから、栗原慶氏をベストティーチャーとして選定した。 |
|
受賞者のコメント |
この度は、過分な賞をいただき、誠に有難うございます。選考に携わっていただきました先生方、ご助力いただきました事務職員の皆様方に対しまして深くお礼申し上げます。今回頂戴しました評価は、鳴門教育大学という素晴らしい環境で、日々多くの方のお支えがあったからこその結果だと受け止めております。 私は、本学に着任以来、工芸担当教員として、陶芸制作を中心とした教育と研究に努めて参りました。工芸制作の礎となるのは、「素材に対する敬意」「身体による技術」「不確実性と創意の調和」といった要素だと考えています。物事が急速に進む時代だからこそ、人間の営為や感覚に直に寄り添うことができる工芸や美術教育の役割は重要だと思っています。 今後も自分のできることを一歩一歩積み重ねながら、学生の皆さん共々学びを高めて参りたいと思います。この度の受賞に恥じることないよう精進し、大学の発展に貢献できるよう尽力していく所存ですので、ご指導ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。本当に有難うございました。 |
| 氏名 | 皆川 直凡 教授 |
| 所属専攻 |
高度学校教育実践専攻 |
| 所属コース |
学習指導力・ICT教育実践力開発コース |
| 写真 | 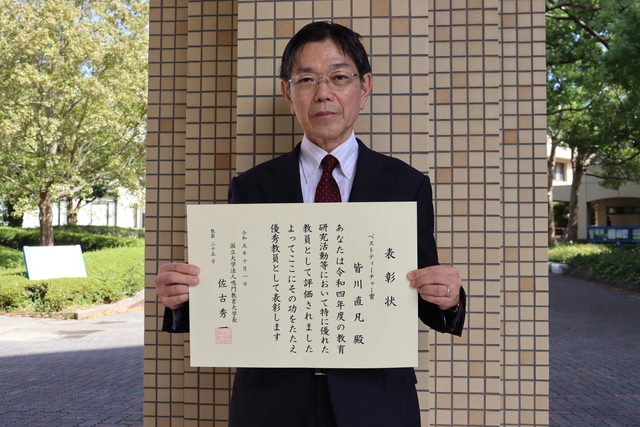 |
|
受賞理由 及び 優れた教育手法 |
皆川直凡氏は、学習指導力・ICT教育実践力開発コースに所属し、専門は教育認知心理学等である。 氏は、1999年10月に着任し、教員志望の学生・院生、および現職教員の院生への教育と研究指導に携わってきた。着任以来多数の学生・院生の研究指導を行い、徳島県下の学校の先生方が2010年7月に開設した勉強会(主題:子どもの発達と教育)に参加し、共同研究を進めている。また、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の基盤となる「自己調整学習」や「言語教育」に関する実践的研究に取り組み、論文発表、講演等により研究成果を公表している。学部教育ではWG主査として「教職実践演習」の開設と実質化に取り組んだ。GPや大学院教育に係るTFの委員を歴任し、連合大学院では副研究科長を務めた。 2022年度に開設された教職大学院遠隔教育プログラムについては、学習指導力・ICT教育実践力開発コースのコース長として遠隔教育プログラム院生の指導に先導的に取り組み、実習校への訪問を丁寧に行うなど、併走型指導実践に貢献している。 以上のことから、皆川氏をベストティーチャーとして選定した。 |
| 受賞者のコメント |
この度は、ベストティーチャー賞をいただき、身に余る光栄に存じます。心より感謝申し上げます。支えてくださっている皆様のお陰と感じております。 私は、教育認知心理学の理論と方法に基づいて学習者の心理を探究し、児童生徒の最近接発達領域を考慮しつつ個別最適化を図り、自律的で協働的な学びを創造する教育に取り組んできました。近年は、その一層の充実のためICTの活用を試みています。私が志向するのは、学びを深め、人間形成に資する教育です。その一環として、短詩型「俳句」の創作と鑑賞を通した心の交流に関する研究とその教育実践にも取り組んできました。昨年度からは、教職大学院遠隔教育プログラムにおける指導にもに全力で取り組み、院生のニーズの把握に努めています。 院生・学生の皆さんの真摯な学習態度に接する中で、多くを学ばせていただいています。学校の先生方との対話が私の教育研究活動の支えとなっています。今後とも、院生・学生の皆さんのニーズに応えられるよう、本学の発展に貢献できるよう、研鑽を積み重ねてまいります。この度は、本当に有り難うございました。 |
最終更新日:令和5年10月23日








