遊誘財
遊誘財とは?
子どもたちが興味関心をもって惹き付けられ、様々に感じ、気付き、夢中になって遊び込み、そのものの本質やおもしろさに迫り、その中から豊かな感情や多様な学びが得られる、このような、子どもたちを遊びに誘う「環境」を、私どもは「遊誘財」と命名した。単なる素材や教材の「材」ではなく、宝としての「財」である。
- 平成23年2月11日発行 遊誘財リーフレットno.2 「植物・動物」より -
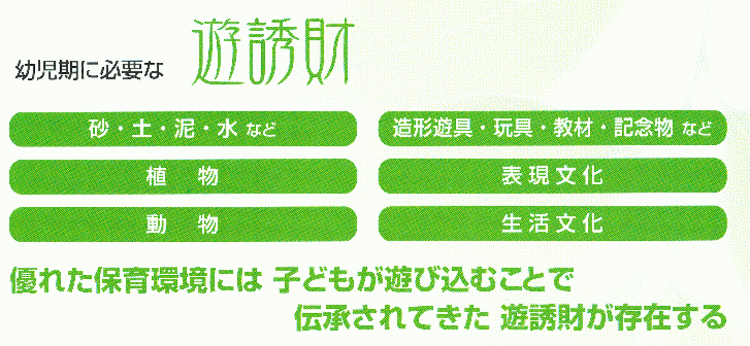
優れた遊誘財は、以下のような流れで遊びを誘発するものと考えます
- 子どもたちに好奇心や興味を刺激し
- 子どもたちが自発的に対象を操作することで対象に変化を引き起こし
- その変化に「なぜだろう?」と考えることをはじめ
- 何かの因果関係やつながりなどに気づきはじめ
- 面白い、驚き、好奇心、感動が生まれはじめ
- 繰り返すなかで知識や技術、思考方法を獲得しはじめ
- 何度もそのような仮説(過程)を繰り返すことで、目的をもって取り組むことをはじめ
- 目的が達成されると達成感や精神的充実感により自信や有能感をもちはじめ
- 自分たちがどのような可能性をもっているかが分かりはじめ
- それらのサイクルが友達同士で行われることで人間を理解し、関係を創造(調整)する力が形成されはじめ
- 協力や協同の能力が育ちはじめ
- 組織・集団(社会)への参加することの大切さや必要性を身に付けはじめ など
(鳴門教育大学名誉教授 佐々木宏子)
リーフレットについて
私共は、幼稚園教育の現場で、幼児教育の根幹にかかわる質の継承の重要性を問いながら実践や研究を重ねていますが、今、この充実した幼児期の子どもの体験の実際を世間にお知らせできていなかったことを感じてきました。子どもの世界は、実に多彩で巧みでおもしろいものです。そこで、本園での環境の中で、子どもが遊び込むことで伝承されてきた学びの事例を、研究紀要とは別にビジュアル的なリーフレットにまとめ、平成22年11月の幼児教育研究会の折から、主題別に公開しています。幼児と遊誘財と保育者との関係性の中で、生成されていく複合的・構造的カリキュラムの様子がご覧になれると思います。
No.1 「砂・土・泥・水など」
No.2 「植物・動物」
No.3 「造形遊具・玩具・教材・記念物など…」
| 研究主題 | 紀要 | リーフレット | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
幼小接続の教育課程開発 (文部科学省指定研究開発学校 第2年次) |
第46集 2012 |
 |
No.3 |  |
詳細はこちら 発行日 2013.2.9 |
|
幼小接続の教育課程開発 (文部科学省指定研究開発学校 第1年次) |
第45集 2011 |
 |
|||
|
保育の質的充実を目指して 「植物」 |
第44集 2010 |
 |
No.2 |  |
詳細はこちら 発行日 2012.2.11 |
|
保育の質的充実を目指して 「砂・土・泥・水など」 |
第43集 2009 |
 |
No.1 |  |
詳細はこちら 発行日 2010.11.20 |
| 保育の質を問う -遊誘財と生活プラン- |
第42集 2008 |
 |
|||
| 保育の質を問う -遊誘財が促す幼児期における 体験の多様性と関連性- |
第41集 2007 |
 |
|||
| 保育の質を問う -遊誘財について考えるⅢ- |
第40集 2006 |
 |
|||
| 保育の質を問う -遊誘財について考えるⅡ- |
第39集 2005 |
 |
|||
| 保育の質を問う -遊誘財について考える- |
第38集 2004 |
 |
|||
