コメンテーター:山下一夫先生・佐藤 亨先生
シンポジスト
教育領域:丸川裕司さん、山下奈緒美さん、木村敦裕さん
司法・矯正領域:後藤田純子さん
丸川裕司さん
1 児童相談所とは
・児童福祉法に基づいて都道府県及び政令指定都市に設置が義務づけられている行政機関
相談機関とは書かなかった。処遇決定をする行政機関である。
・徳島県は、現在、中央児童相談所・南部児童相談所・西部児童相談所の3カ所が設置されている。
行政措置として動かすことで精一杯
・運営は『児童相談所運営指針』(厚生労働省)が基本で各地方自治体の管理の下に置かれている。
・子どもと家庭に関するあらゆる福祉相談に応じる福祉行政機関。
・必要に応じて児童の一時保護・施設入所措置など、行政的権限を執行できる。
2 児童相談所の職員構成
・所長、次長=県庁の管理職
・相談課員=福祉行政1年以上経験者の県行政職員が定期異動で赴任する。
・判定課員=県庁職員の採用試験において心理技師として専門職採用された職員の中から配属される。
(相談・判定課員は社会福祉主事任用規定に基づいて自動的に児童福祉司になる。)
・総務課員=児童相談所内の事務全般を担当する県行政職員。
・一時保護所指導員=事務職は県行政職員が勤めるが、指導員・栄養職員は専門職採用の中から配属される。
・その他臨時職員多数(電話相談業務、虐待対応、夜間電話対応、一時保護所指導員補助職など)
・外部委託職員=(精神科医、小児科医、弁護士など)
・短期(1年間)研修教員=(一時保護児童の学力保障のため、小中学校教員が一時保護所に2名常駐)
3 相談内容
相談の種類は子どもの福祉に関する各般の問題にわたるが、大きくは養護相談、障害相談、非行相談、育成相談、その他の相談に分類される。
○ 養護相談=家庭環境や家族の状況などにより児童養護施設収容が必要な児童についての処遇判断。
被虐待児の保護と家族への矯正指導・家庭機能回復支援。
※特に虐待対応については、児童虐待防止対策の一層の充実・強化を図っていくことが必要。
昨年度は200件近く。2500〜2780件のうち過半数は障害相談。全国的にはDV、徳島県ではneglectが多い。
・児童家庭相談に応じる市町村に対して適切な支援を行う。
・医療、保健、法律その他の幅広い専門機関や職種との連携強化。
・司法関与の仕組みの有効活用等により、迅速かつ的確な対応を図る。
・親子再統合の促進への配慮。
・被虐待児が良好な家庭的環境で生活するために必要な保護者も含めた家庭への支援。
○ 障害相談=生育歴、周産期の状況、家族歴、身体の状況、精神発達の状況や情緒の状態、保護者や子どもの所属する集団の状況について調査・診断・判定をし、必要な援助に結びつける。
○ 非行相談=司法の定める触法少年や専門的な福祉処遇が必要な非行事例に関する福祉的援助。非行傾向の顕著な児童に関わる地域支援や機関連携チームへの助言指導。
○ 育成相談=性格行動、しつけ、適性、不登校等に関する相談をどのような機関が適切に対応するか判断し、送致あるいは紹介する。
昨年度改正。実際の業務は受け付けをしても、市町村の福祉課で対応、インテーク面接のみ。
○ その他の相談=里親希望に関する相談、上記のいずれにも含まれない相談等。
4 相談の流れ
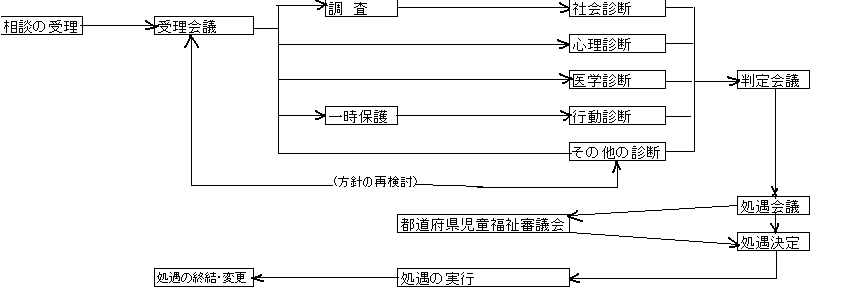 |
・施設入所措置
・助言指導、継続指導
・里親委託
・他機関への送致
6 児童福祉司の仕事
(1)担当区域内の子ども、保護者等から子どもの福祉に関する相談に応じること
(2)必要な調査、社会診断を行うこと
(3)子ども、保護者、関係者等に必要な支援・指導を行うこと
(4)子ども、保護者等の関係調整を行うこと
※ 児童福祉司の行う通所面接や家庭訪問、機関・施設訪問は、調査・情報収集・助言指導・説得・交渉・情報伝達・処遇通知など様々な目的がある。
山下奈緒美さん
・修了4年目、臨床心理士として3年目。
・10年現場の教員として教育相談を担当。スクールカウンセラー4人と会う。
・スクールカウンセラーがいないときには、スクールカウンセラーとしての役割もすることになる。教員としても求められる。
・井上先生と入谷先生のスーパーバイズを受けた。井上先生には、クライエントの不利益にならないようにバイズしていると言われた。
・育ててもらっていることに甘えてはいけない。
・院生が増えたのですが、自分から求めてバイズを受けなければと思う。
・やはり達成感もある。一人で入っていくときに、どうしたらよいかと思う。
・スクールカウンセラーは、中学校が拠点校だが、学校にいる臨床心理士である。
・教育のことだけではつとまらない。
・知っていって初めて、一生を見通したこの時期何ができるかで見られる。
・乳幼児検診からスクールカウンセラーの学校までつながっている。
・保健士、ソーシャルワーカーとつながっている。
・学校での家庭訪問以外の対象に保健士さんは行ってくれる。
・不適応の半数は、発達が絡む。子であったり、親であったり。
・医療での検査ができていないと、アセスメントができない。
・緊急支援との関わり、整備に危機感を持っている。
・学校での対応を誤らないように、学校に戻すことではない。
・一人で(スクールカウンセラーとして)、入っていく。先生方とつながることから。
・教員と同じく、1年目でも10年目と同じような力量を求められる。
・アセスメントを求められることで、認められていることが分かる。
・院生さんに来てもらっているが、抜けているから穴を埋める。
・クライエントに不利益にならないように。
・最新のものを学び続けること、医療の現場にいるから何とかできている。
・学校ではどうやって入手していくかが課題である。
木村敦裕さん
・適応指導教室、指導補助 三重県伊賀市教育研究センター。小学校20校、中学校10校で100人前後。
・常時来るのは10人ぐらい、各校から1割くらいが来る。
・もともと小学校の2階部分を使用。学習室はもとの図書室、相談室はもとの放送室。
・学習タイムを重視している。基本的な学習能力が低い。学習保障をすることが仕事である。
・個別対応もしている。
・フリータイムには、どうしても室内に居たがる。男子ではテレビゲームなど。前日から声がけをして外へ出すように。
・学校の嫌な部分を除いたところ。
・ランチタイムでは、全員が一緒に「いただきます」をしたいが、なかなかできない。
・学校の担任の先生が訪ねてくるが、嫌われている。子どものことを気にしないで、しゃべってくる。
・教室に来ている子どもを中心にかかわっている。
・担任の先生の気遣っている思いも分かるが、子ども達が離れていく。
・学校に行っていないのだから、学校で学べないことをも学んでほしい。
・再登校については、うまくいったのは全体の2割。本人だけの問題ではない。
・適応指導教室の存在価値は、子ども達のいる場所。
・甘え、依存と扱わないように包んで、包んでいくようにして。
・カウンセラーと指導補助の両方をやっているので、苦労しているところである。
後藤田純子さん
・生活安全課少年補導職員の仕事、電話相談、非行少年のカウンセリング
・はじめは、嘱託職員として勤務、その後、採用試験を受けて合格し、警察学校を経て警察署に勤務。
・非行臨床の分野で、補導、カウンセリング、電話相談を担当。
・1回しか会えない人もいるので、会ったときに心に残る言葉をかけたいと思っている。
・ボランティアの方と一緒に動いたり、防犯キャンペーンを行ったりしている。
・本部と各警察署では、署に出ると、一人の子どもと継続的に関わることは難しい。
・会ったときに臨床心理士として関わることができればと思う。
・補導される子どもは、何回かされている。慣れている子どもが多い。プライベートなことも話をしてくれるが深まらない。
・触法少年と話をして思うことは、受容感になってしまうが、違うことを話をする場合もあるが、バランスが難しい。
・動機が流されているなと感じる。順序立てて言葉をつないでいくこと。
・呼ばれた子どもには、悪いことは悪いことと伝えて、再犯がないようにと考えている。
・非行の子どもには、警察に来ることが、またカウンセリングをすることがすることが、ひとつの枠になっている。
・心理の勉強をした人がいることが、役に立つと言うことを思ってもらうことができればと思っている。
<コメント>
佐藤亨先生
・現場での保護観察、児相での虐待、現場での力量が問われてきている。
・マンパワー、訓練はなかなか保障されていない。
・一人一人の自助努力が求められる。何とかしてしまっているところも問題だが、力をつけることも必要である(→丸川さん)。
・努力を院の中でも、その後もされている。発達医療のところを勉強しなければと感じた(→山下さん)。
・適応指導教室、楽しいところ、たいへんなところ、相談のあとにしからなければならない難しさ(→木村さん)。
・たいへんだけれども、がんばってね。一過性の指導で終わる。便りのないのはと思う。街頭指導、触法少年の補導、警察が調査権を持つ、子ども達の気持ちを大切に(→後藤田さん)
・共通して言えること、組織として、組織の中で活動していく。組織としてのニーズと、臨床心理士として一人一人を大切にしたいという思いとの間の難しさがあるのではないか。組織としてある程度のニーズを満たしてから、その後に自分のやりたいことがで着てくると思う。
山下一夫先生
・組織と私が大きなテーマ。
・1やりたいことがあったら、10組織のためにやれ。先ず、いろいろなことをして認められてから。
・仲間を見つけられるか、応用問題として関わられるか。
・服装のTPOと一緒で、先日、ヘソ出しの院生がアンケートの依頼に来た。組織内での働き。
・保護者面接、話し方、聴き方のTPO。
・小此木先生の本で、スーパービジョンをやっていて、Klein派の人はnegativeな面を見ていく、間主観主義の人は共感性を重視、クライエントさんの立場になっているが、なかなかみえてこない。2つ足して割ることができれば。統合していくことができれば。
・共感性を大事にしていても。立場が分かっていて、調べていく、共感性を持ちながら。
・木村さんの学校の先生が嫌われているのは、代表して嫌われていると言うこと。
・学校の先生は嫌われていても、不登校の子は、親が、カウンセラーが悪いとは言わない。担任が代表して悪いと言っていく。学校の先生は、嫌われても関わっていく。共感性と受容性を持ちながら、嫌われながら関わっていく。学校の先生のたいへんさ。
・開き直って、めちゃくちゃするのではなく、関係を切らないこと。わかい臨床心理士を目指す人は心と心を大事にするが、しゃべり方がへた。
・児相の本質、問題点が丸川さんの話から見えている。児相も90年代から2000年代より不登校から虐待へと変わってきている。今できるところで、頑張ってきている。
<フロアからの質疑を含めて>
川瀬公美子さん
・感想として。嫌われても関係性を切らずにとは、担任や管理職との関わりをと感じた。1回しか会わないというと、補導されたことを話をしてくれることもある。表向きの言葉ではなく、本当の中での話をされたかが分かる気がする。最初に誰かと会って話をすることの大切さ。今のアセスメント、これからどうなるのかも考えて関わる。
末内先生(司会)
・村瀬さんの補導員をされていてのコメントと重なることもある(→後藤田さん)。私服で歩いていて、同じ目線で話をしようとしている。うそをいわれる。一瞬でも関わりができれば。
佐藤亨先生
・ウソをつかれるのは仕方がない。鑑別所に入ってくると、こんなに素直に話してくれるのかと思う。聞くだけ聞いて、返事がないのを伝えていく。受容だけではやってはいけない。事実は事実として聞いていく。100%は無理で、10回に1回ヒットするくらいの気持ちで関わる。
・たいしたことはできないが、たまにすごく大事だったりする。関わっていくようにすることが大事では。
山下一夫先生
・高校の時、パチンコ屋に行っていた頃、年だけでなく年と干支を聞かれると言うことで、「20才、うさぎ」と覚えていた。使わずに来た。何か、明るさ、何人かに一人いるかということ。
・挨拶は明るく、ノー天気で積極的に関わっていく。嫌われても関わっていく。関わっていくときの関係性。明るいところ、良いとこ探しをしていく。長い目で見ていくことが大切なのでは。
丸川さん
・通告児童との関わり、保護者付きで会う。非行相談、育成相談、面談、面接を顔をつきあわせて行う。養育相談は、、心理相談は成立しない。最初は教師の顔で接していたが、臨床心理士という中身を使う。社会福祉士の研修をどんどん受けた。福祉ワーカーとの関わりを、理想としてみることができるようになってきた。困っている子どもと関わっていくことができるようになった。
・土台を作ってきている上に、鳴教でのことは、すぐに使えるものではないが、何度か振り返っているうちに、心理療法、カウンセリングを使わないうちに、心をさわらないうちに、やれることがあるのではないか。環境を整え、福祉的な環境をサポートしてあげる。現場のニーズ、組織としてのニーズにつながるのではないか。
坂本文隆さん(16期)
・ウソは良くつかれる。補導員に勝った、勝ち負けにこだわる。信じて良いんだねと確認する。本気で、真剣に怒る。真っ赤になって怒る。そのあとはウソはつかなくなる。カウンセラーはウソをつかれても良いが、現場はウソをつかれては困る。
山下一夫先生
・本気になれるかが勝負所。先生もカウンセラーもと思う。
山下奈緒子さん
・スクールカウンセラーとして入っていて、最初は非社会的な子どもが多かったが、その後に反社会的な子どもを連れてきてくれるようになった。三者の関係性、四者の関係性、養護の先生が入ってくると。担任の先生が三者で関わると、ゆとりが出てくる。何度か(担任が)連れてくると、関わりが変わってくる。熱さを持ってほしい。
佐藤亨先生
・(鑑別所の子どもに聞くと)印象に残っている先生は、ぎゃあぎゃあ言って、がみがみ言う先生、あの先生良かったよなあと言う。見て見ぬふりをする先生が嫌だったという。ウソをつかれたとき、真っ赤になって怒るという話を聞いて。ぶっちぎれておこったら、しばらく来なかった、アルバイトを始めたんだという。その人との関係が切れないようだ。嘘をつけない、その人との関わりを考えれば。
・非行少年、案外弱っちいのが多い。その場を逃れるためにウソをつく。
木村さん
・(適応指導教室で)非行系の者も受け入れるようになった。かき回す、その場しのぎのウソを言う。やりたくないというと少しましになった。非社会系の子が反社会系に、非行系の子が入ってくると流れる。
<最後に>
丸川さん
・院2年後の児相の3年間。社会福祉学で隙間を埋める。想像を絶する家庭の中で生きようとしている子。
山下さん
・帰ったら関われる、悩まれるスクールカウンセラーとつながってほしい。
木村さん
・臨床家としてよりも、社会人として
後藤田さん
・新しい仕事をして数ヶ月、これからも頑張っていきたい。
佐藤亨先生
・勉強しなきゃなあと思う。
山下一夫先生
・臨床心理を勉強、心が大事だが、絶対ではない。天狗になってはいけない。今、この子に何ができるのか、臨床とは違う場面で関わるかも知れないが、嫌われても関わっていくときに。先日のドキュメントで、中年の男性教師が、燃え尽きてしまった先生の話が放送されていた。学校の大変さ、一生懸命だが。愛を感じない、愛していない。どこかで良いところ探しを、あたたかさをと感じた。
末内先生
・ピアスーパービジョン、現職の先生のパワーをいただくことを感じた。