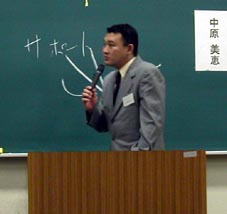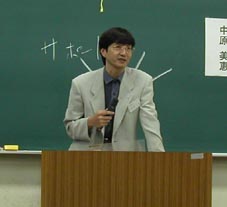| 受付9:00~9:30 |
|
研究発表9:30~12:30 自由研究発表 1~4分科会
第1分科会 座長:森田洋司(大阪市立大学)
・ガイダンス的生活指導と自己指導能力について
石田匡志(鳴門教育大学大学院)藤枝 博(鳴門教育大学)
・中学校における暴力予防プログラム開発の基礎的研究
岡村一利(兵庫教育大学大学院)上地安昭(兵庫教育大学)
・少年と刃物に関する一調査
木村友美(日本女子大学大学院)清水賢二(日本女子大学)
・中学生の心の拠り所と問題行動兆候に関する研究(2)
寺田智礼(加須市立加須北中学校)田中雄三(鳴門教育大学)
葛西真記子(鳴門教育大学)
・中学生の自尊感情・規範意識と親役割に関する研究
永尾修一(鳴門教育大学大学院)葛西真記子(鳴門教育大学)
・男子高校生における親子関係についての研究
吉廣江利子(鳴門教育大学大学院)葛西真記子(鳴門教育大学)
総括討論 |
第2分科会 座長:田中雄三(鳴門教育大学)
・家族援助をとおして学校不適応の改善を試みた一例
麻喜総一郎(宮城県迫桜高等学校)
・スクールカウンセリングにおける面接の現状と課題
熊谷圭二郎(宮城県広瀬高等学校)葛西真記子(鳴門教育大学)
・不登校経験者の自己肯定感について
角田智恵美(鳴門教育大学大学院)入谷好樹(鳴門教育大学)
・モデル(同一化対象)の存在が中学生のアイデンティティの形成
と行動に及ぼす影響
長谷由香(鳴門教育大学大学院)田中雄三(鳴門教育大学)
・適応指導教室における指導員の在り方に関する一考察
渡邉智子(千葉大学教育学部附属教育実践総合センター)
総括討論 |
第3分科会 座長:二宮 皓(広島大学)
・アドラー心理学における学級経営プログラム(2)
会沢信彦(函館大学)
・小学校の規範意識と家族関係に関する研究
栗田 稔(鳴門教育大学大学院)田中雄三(鳴門教育大学)
・高等学校における参加体験型人権学習の効果に関する実証的
研究
大西雅人(鳴門教育大学大学院)吉井健治(鳴門教育大学)
・話し合い活動を重視した学級活動による学級集団経営への効果
久保田員生(鳴門教育大学大学院)小坂信嗣(鳴門教育大学)
・開かれた学校づくりの中での生徒指導のあり方
中田 哲(大阪府立香里丘高等学校)
・生徒指導の総合化
板東秀則(徳島県上坂町立上坂中学校)
総括討論 |
第4分科会 座長:横山利弘(関西学院大学)
・担任役割の心理に関する一考察
安居院みどり(横浜市立十日市場中学校)
・小学校における「総合的プログラム」による道徳授業について
加藤英樹(鳴門教育大学大学院)小坂信嗣(鳴門教育大学)
・長期研修生(生徒指導・教育相談)へのBasic Encounter Group
の適用
清水幹夫(法政大学)
・幼児期の道徳性の芽生えについて
前田美代(鳴門教育大学大学院)浅野弘嗣(鳴門教育大学)
・教育的タクトのあり方に関する一考察
三橋謙一郎(徳島文理大学)
・中学生期の生徒指導における「叱ること」に関する一考察
山口 孝(鳴門教育大学)藤枝 博(鳴門教育大学)
総括討論 |
|
 |
| 第2分科会:麻喜総一郎発表場面 |
 |
| 第2分科会:熊谷圭二郎発表場面 |
 |
| 第2分科会:角田智恵美発表場面 |
 |
| 第2分科会:長谷由香発表場面 |
 |
| 第2分科会:渡邉智子発表場面 |
|
|
| 課題研究13:00~15:00 |
|
Ⅰ チームサポートの具体化・実証化Ⅱ
パネラー:森嶋昭伸(国立教育政策研究所生徒指導研究センター)
相模健人(愛媛大学)
小谷一良(兵庫県教育委員会)
中原美恵(千葉工業大学)
コーディネイター:山下一夫(鳴門教育大学)
生徒指導・教育相談において、教師・保護者・関係者等によるチー
ムサポート(チーム援助)や組織的対応は当然のことといえます。前
回の日本生徒指導学会においても同じテーマで課題研究を行いまし
た。(その内容は、「月刊生徒指導」2002年2月号,3月号にまとめ
られています)今回も引き続き,チームサポートを取り上げ,その現状
と課題について様々な観点から話し合いを行いました。
・深刻な問題行動等(その前兆を含む)を起こしている個別の児童生
徒に対し,その解決に向けて,関係機関等がサポートチームを編成
し,機動的・実効的に対応していくことが,問題行動等の予防や解決
に今日求められていることである。そうしたサポートチームの編成・組
織化の仕組みを内に持った構造的なネットワークを構築することは,
我が国の地域社会における共通の課題であり,この取り組みが,問
題行動等の予防や解決のみならず児童生徒の健全育成を導くカギ
になると考える(森嶋)。
・学校を「児童生徒,教職員,保護者,地域などの関係の総体」とした
システムとしてみるとき,そこには学校における様々な問題に対する
ための「資源」が内在していると考えられる。今回の課題研究では,筆
者がスクールカウンセラーとして,システムズアプローチを用いて関わ
った保健室登校の事例を紹介する(相模)。
・問題行動を起こす個々の児童生徒に着目して的確な対応を行うため
には,学校,教育委員会のみならず,ふさわしい関係機関との連携等
,地域ぐるみの取り組みが効果的である。そこで,学校が行動連携に
踏み出す状況づくりのために,学校からの日常的な相談対応と学校の
秩序維持等の緊急的な課題に対する支援体制を組織することとした。
学校をサポートすることで子どもをサポートすることになる(小谷)。
・「不登校」を「共存の意志のくじけ」という視点で捉え,ある小さな市の
スクールアドバイザーおよびスクールカウンセラーとして,「不登校の」
チームサポートの具体化に取り組んできた。まだ途上ではあるが,5
年間の歩みを話し,学校を中心とした地域チームサポートを具体化す
るポイントは何かを共に考えたい。また,そうした取り組み自体が「共
存への意志」を育む支援であるという側面についても検討したい
(中原)。
|
 |
| 課題研究Ⅰ:森嶋昭伸発表場面 |
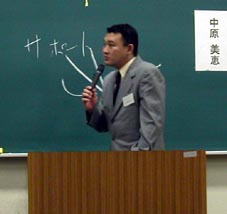 |
| 課題研究Ⅰ:相模健人発表場面 |
|
Ⅱ 新しい学びの開発と生徒指導
パネラー:西川敏之(山口県大島郡教育事務協議会)
七條正典(香川大学)
石川正一郎(愛媛県公立中学校スクールカウンセラー)
天野順造(高知県南国市立香長中学校)
村川雅之(鳴門教育大学)
コーディネイター:小泉祥一(東北大学)
山口 満(筑波大学名誉教授)
21世紀における新しい学校知のあり方や学ぶことへの意欲をなくし
た子どもの増加などと関わって,学校における子どもの学びの転換を
図ることが必要であると言われています。
一方,文部科学省大臣によって「学びのすすめ」のアピールが行わ
れるなど,確かな学力の形成をはかることの重要性が改めて指摘さ
れています。
こうした状況の中で,新しい学びをどのようにとらえればよいのかそ
れと生徒指導との関係をどのようにとらえ,実践すればよいのか。今
求められている学力形成と生徒指導との関係のあり方を改めて総合
的に検討し,今後の生徒指導の課題や方法について考えてみたいと
思います。
|
 |
| 課題研究Ⅰ:小谷一良発表場面 |
 |
| 課題研究Ⅰ:中原美恵発表場面 |
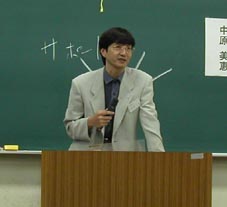 |
| 課題研究Ⅰ:山下一夫発表場面 |
|
| |
|
| 鳴門生徒指導学会・生徒指導講座同窓会総会懇親会17:00~ |
鳴門グランドホテル |
|
|