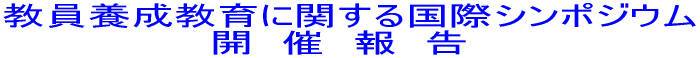
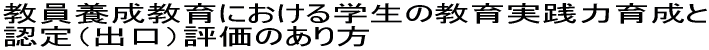
![]()
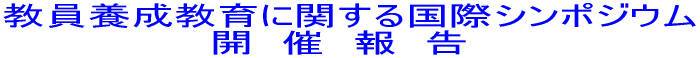
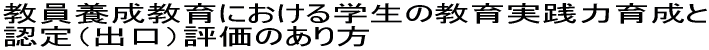
![]()
今日,変化する学校現場の状況のなかで,教育実践力を有する質の高い教員が求められている。教員養
成を目的とする大学・学部が,学生の教育実践力を培うためにカリキュラムや授業の改善を不断に図ってい
くことは,社会的責務であると考える。
これまで,教員養成教育の目標としての教育実践力育成は,理念的な方向目標としての段階にとどまりが
ちであった。今後は,教育実践力を到達目標としてとらえ具体的な到達(評価)基準(スタンダード)を明確に
定めてカリキュラム・授業を展開するとともに,教員養成の成果について基準にもとづいて説明責任を果たし
ていくことが求められる。
こうした問題意識から,教員養成教育改革のために,教育実践力の内容とその評価基準のとらえ方及び
学生の教育実践力の認定(出口)評価とカリキュラム評価のあり方について,シンポジウムを開催した。
【 日 時 】 平成19年12月7日(金) 13:00~17:30
【 場 所 】 鳴門教育大学 地域連携センター多目的教室
【 参 加 者 】 50名 (教育関係者・大学関係者26名,本学教職員20名,大学院生4名)
多数のご参加をいただき,ありがとうございました。
●13:00 開 会 |
|
| 主催者代表挨拶 | 総合司会 |
| 鳴門教育大学長 高橋 啓 | 鳴門教育大学 言語系(国語)教育講座 准教授 余郷 裕次 |
 |
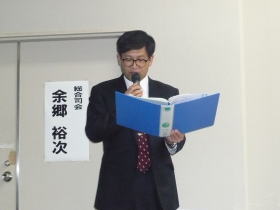 |
| ●13:10 | |
| 基調講演 「小学校教員養成を目指した横浜スタンダードの開発」 (約50分) | |
| 講 師 横浜国立大学 教育人間科学部 教授 海老原 修 氏 |
|
 |
 |
| ●14:00 | |
| 事例報告 「『授業実践力評価スタンダード(鳴門スタンダード)』を活用した 教員養成コア・カリキュラムの展開」 (約20分) |
|
報告者 鳴門教育大学 社会系教育講座 准教授 梅津 正美 |
 |
|
14:20~14:30 休 憩 |
|
| ●14:30 | |
| パネルディスカッション(約160分) | |
| 司 会 鳴門教育大学 学長補佐 西園 芳信 |
指定討論者 鳴門教育大学 准教授 梅津 正美 |
 |
 |
パネリスト 公州教育大学校(韓国) 教授 李 明珠 氏 |
パネリスト 北京師範大学教育学院 (中国) (写真左側から)教授 郭 華 氏,研究員 樊 秀麗 氏 |
 |
 |
パネリスト 島根大学 教育学部 准教授 加藤 寿朗 氏 |
パネリスト 鳴門教育大学 芸術系(音楽)教育講座 准教授 長島 正人 |
 |
 |
| ●17:10 | |
| フロアーとの質疑応答 (約15分) | |
 |
 |
| ●17:30 閉 会 | |
教員養成教育に関する国際シンポジウムの成果と展望 社会系教育講座 准教授 梅津正美
平成18年度特色ある大学教育支援プログラム(特色GP)推進事業の一環として,「教員養成教育に関する
国際シンポジウム」が,平成19年12月7日(金)に本学で開催された。主題は,「教員養成教育における学生
の教育実践力育成と認定(出口)評価のあり方-教育実践力評価スタンダードの開発と意義-」である。シン
ポジウムには,日本と韓国,中国の教師教育関係者約50名の参加者を得ることができた。
基調講演者である横浜国立大学・海老原修教授は,「教師としての基本的素養」「児童理解」「学級経営」
「教科指導」「児童の学習状況の評価」「学校運営」を柱に教師としての資質・能力の観点別達成目標と評価
基準を定めた「横浜スタンダード」に準拠して,職能を4カ年にわたる日常的・継続的教育実習と集中型教育
実習の両者を中心育成していく初等教育カリキュラムの特色を説明された。
続いて,筆者が,「授業実践力評価スタンダード」を活用したマイクロティーチングを組み込んだ「初等中等
教科教育実践Ⅱ(社会科)」の実践事例を報告した。
パネルディスカッションでは,本学・西園芳信教授の司会のもと,教育実践力とはなにか,教育実践力はど
のような実践を通じて育成できるのか,教育実践力はどのように評価できるのか等を考察課題に活発な提言
と議論が展開した。韓国・公州教育大学校の李明珠教授は,教員養成の質管理体制の強化を進める国策の
もと,教員任用試験において,授業能力評価の厳格化が進んでいる現状をふまえ,初等教員養成を担う教育
大学校が,授業能力育成をめざす教育課程改革と,学生の成績評価の厳密化を図ってきていることを説明さ
れた。中国・北京師範大学の郭華教授と樊秀麗研究員は,「4+2」模式カリキュラムの内容と特質について
論じられた。「4+2」模式とは,教員養成系の学生と非教員養成系の学生を区別しないで,学士課程4カ年で
各専門分野を修めさせ,修士課程2カ年で教職関係科目を習い,教育実践を積ませるカリキュラムである。中
国では,専門の学芸と教育実践の両方に長けた研究型教員を,修士号を基礎資格に養成しようとしているこ
とが理解された。島根大学の加藤寿朗准教授は,1年生から4年生までの継続的・系統的な「学校教育実習」,
学校での学習支援,ボランティア活動等を通じた「1000時間体験学修」,学生の学修状況と教師としての資質・
能力の向上を評価基準にもとづき追跡するカルテである「プロファイルシート」の実践内容と意義を説明された。
本学の長島真人准教授は,到達目標としての教育実践力は,「授業実践力」「生徒指導力」「連携力」により構
成されるとの仮説を提案された。そして,各能力ごとに評価規準(スタンダード)を開発し,その規準にあわせた
作業課題と評価基準の開発が一貫してなされるべきであると提言された。
本シンポジウムを通じて,筆者は次の3つのことを教員養成教育改革の課題として把握した。すなわち,①教
育実践力評価スタンダードは,授業実践の事実を通じてつかみ評価できる能力内容を確定し開発していくこと,
②教育実践力評価スタンダードは,学生が自己の教師としての能力を省察する参照点であり,その内容と活
用には修正可能であることを前提とした弾力的運用が求められること,③スタンダードにもとづく明確な作業課
題とその達成度の評価基準および自己評価・他者評価機能を教員養成カリキュラム・授業に体系的に組み込
んでいく必要があることである。
本シンポジウムを契機として,今後,日本・中国・韓国を結ぶ東アジアにおける教員養成教育改革のための
フォーラムが形成されていくことを期待したい。
シンポジウム報告書の送付を希望される方は,
送付先の住所・氏名・電話番号をe-mailでご連絡ください。
e-mail : gp@naruto-u.ac.jp
| <BACK> |